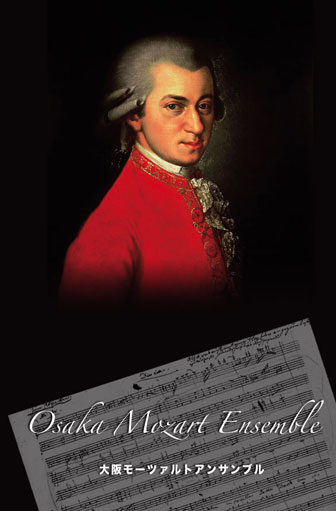モーツァルトの自筆譜には、ファゴットは緩徐楽章とメヌエットのトリオにしか使用されていない。交響曲第 25 番ト短調 KV 183 (173dB)以前に作曲された交響曲でファゴットパートがある 3 つの交響曲を見てみると、交響曲第 12 番ト長調 KV 110(75b)は、緩徐楽章にだけ独立したファゴットパートを作曲し、他の楽章にはファゴットの指定はない。
真作ではない可能性もある交響曲ヘ長調 KV 76(42a)は、緩徐楽章は完全に独立したファゴットパートが書かれ、メヌエットは、主部・トリオともバスパートと同じ。第一楽章とフィナーレは、基本的にはバスパートをなぞっているが、オーボエ、ホルンとともに和音を構成する部分もある。交響曲第 26 番変ホ長調 KV 184(166a)では、第一楽章は、フルート、オーボエと和音を構成するところ以外は、バスのパートをなぞるだけだが、緩徐楽章、フィナーレは、管楽器の一員として作曲されている。
ハイドンの場合でもそうだったように、速い楽章ではファゴットをバスに重ねることが当時の習慣であったことから考えて、ファゴットの指定がない楽章においても、ファゴットは、バスと同じパート譜で演奏するべきだと考える。J.A.アンドレの 1833 年の手書きのカタログによると、「本物の写譜から起こしたモーツァルト作曲のパート譜、VI.177――交響曲、ヴァイオリン 2、ヴィオラ 2、バス、オーボエ 2、ファゴット 2、ト調のホルン 2、変ロのホルン 2」とある。残念ながら、これが現存していないので、ファゴットが実際の演奏でどのように扱われたのかわからないが、大変興味深い別の文献(アロイス・フックスの総譜)がプラハ大学に保管されている。この総譜には、両端楽章にもファゴットのパートが書き込まれているが、バスパートとは少し異なっている。第 1 楽章の静寂な場面で休ませ(弱音指定でも動きのある個所はバスパートと同じ音が書かれている)、フィナーレでは弦楽合奏になる個所は休ませている(ただし、冒頭の弦楽器のユニゾンはファゴットに参加させている)。メヌエットは管楽合奏になるトリオのみで、主部は休ませている。この総譜はモーツァルトが意図したものなのか当時の習慣だったのか、解釈が難しいが、私には、メヌエットの主部で休ませる必然性がわからない。トリオでファゴットをはじめて登場させることが、それほど効果的であろうか。フィナーレの再現部の弦楽器のユニゾンではファゴットを休ませているのに冒頭では重ねている理由もわからない。本日の演奏では、メヌエットの主部はバスにファゴットを重ね、フィナーレの冒頭は休ませてみようと考えている。
ヴァンハル、ハイドン、モーツァルトのト短調交響曲に共通する一つの点として G(ト音)管のホルン 2 本と並行調の基音となる B(変ロ音)管のホルン 2 本を使用している点である。モーツァルトはこれまでにも 4 本のホルンを使った交響曲を作曲していた。交響曲第 18 番ヘ長調 KV 130、交響曲第 19 番変ホ長調 KV 132 がそうである。前者は、2 本の F管(ヘ音)ホルンと属調の基音となる高い C 管(ハ音)ホルン 2 本が、後者には、2 本の低い Es(変ホ音)管ホルンと半分の長さの高い Es 管ホルンが 2 本使われている。ハイドンも、交響曲第 13 番ニ長調、第 31 番ニ長調、第 72 番ニ長調に 4 本のホルンを使用しているが、こちらは 4 本とも D(ニ音)管のホルンである。一方、ヴァンハルは短調の交響曲に様々な組み合わせのホルンを使用している。1764~1767 年に作曲した交響曲ホ短調e1 に 2 本の E 管(ホ音)ホルンと 2 本の G(ト音)管ホルンを、1767~1768 年に作曲した交響曲ニ短調 d1 に、2 本の D 管ホルンと 2 本の F 管ホルンを、1769~1771 年に作曲した交響曲イ短調 a2 に、2 本の A(イ音)管ホルンと 2 本の C 管ホルンを、1773 年~1774年に作曲した交響曲ニ短調 d2 に、2 本の D 管ホルンと 2 本の F 管ホルンに加えて 1 本の A管ホルンを使用している。1771 年~1772 年に作曲した交響曲ホ短調 e2 では、1 本の E 管ホルンと 1 本の G 管ホルンを、1773 年~1774 年に作曲した交響曲イ短調 a1 では、A 管ホルン、C 管ホルン、E 管ホルンを 1 本ずつ使用しているが、後年、モーツァルトが交響曲第 40番ト短調でG管ホルンと B管ホルンを 1本ずつ使用した例の先駆けになっている。