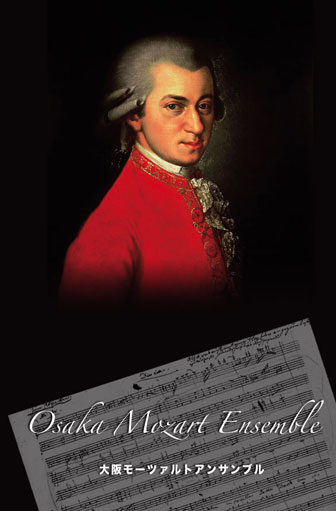アウエルンハンマーとモーツァルト
大阪モーツァルトアンサンブル 武本 浩
1781年3月16日、モーツァルトは、ザルツブルク大司教ヒエローニュムス・コロレードの命に従い、ヴィーンに赴いた。翌日に書かれた父への手紙の中で、ヴィーンに無事到着したが、食事は、料理人や菓子職人と一緒の末席で取らねばならず、食卓では下品でばかばかしい冗談が交わされるので、食事中はひと言も口をきかないで食事が終わるとすぐ引き上げていると報告している。3月24日付の父への手紙に、実際に送られたのは28日以降であるが、ヴィーンでクラヴィーアの最初の弟子となるアウエルンハンマーの名前が初めて登場する。
天気がよくなり次第、フォン・アウエルンハンマー氏とその肥満令嬢の邸に行きます。
ヨハン・ミヒャエル・フォン・アウエルンハンマー氏はオーストリアの実業家で、モーツァルトがヴィーン到着早々に訪問していることから、父レーオポルトと親交があったのであろう。モーツァルトの手紙によると、アウエルンハンマー氏は、1782年3月22日の午後6時半に亡くなるまで、何度かザルツブルクのレーオポルトと手紙のやり取りをしていた。彼の「肥満令嬢」が本日の演奏会のテーマになっているヨゼーファ・バルバラ・アウエルンハンマーである。彼女は、1758年9月25日生まれ、モーツァルトの2歳年下である。モーツァルトの弟子になるまでは、ゲオルク・フリードリヒ・リヒター、ないしヨーゼフ・リヒターというヴィーンの音楽家に学んでいた。モーツァルトの死後はレーオポルト・アントーン・コジェルフの門下に入っている。1781年6月8日、モーツァルトは、アルコ伯爵にお尻を足蹴にされて戸口から追い出され、ザルツブルクの宮廷から解雇された。これで晴れて自由の身になったモーツァルトは、音楽の都ヴィーンでの活動を本格的に開始したのである。
1781年6月27日付の父に宛てた手紙にアウエルンハンマー嬢のことが詳細に述べられている。
ぼくはほとんど毎日、昼食後、アウエルンハンマー氏の家に行きます。――その令嬢ときたら化け物のようなブスです!――でもうっとりとさせるような演奏をします。ただ彼女には、カンタービレで弾く、本当の繊細な歌う様式が欠けています。彼女はなんでも爪弾きしてしまうのです。――彼女は自分の方針を(こっそり内緒で)打ち明けてくれました。それは、あと2、3年みっちり学び、それからパリに行って、音楽を職業とする、というものです。――彼女は言いました。「私は美しくありません。ああ、それどころか醜いです。年収3~4000グルデンの官庁のお偉方などと結婚したくはないし、他の男を手に入れるなんてできそうもない。だから、このまま独りでいて、自分の才能で生きて行きたいんです」と。これはもっともなことです。そこで彼女は、その計画を実現するために、ぼくの助けを求めたわけです。――でも彼女はあらかじめそれを誰にも打ち明けたくないのです。
オペラは、なるべく早く送ります。トゥーン伯爵夫人がいまだに持っていて、目下、彼女は田舎にいます。――ともあれ変ロ長調の四手のためのソナタと、二台のクラヴィーアのための協奏曲二曲を写譜して――至急送ってください。
8月22日付の父への手紙には、レーオポルトが信頼を寄せているアウエルンハンマー一家のことがこと細かく記されている。父親のヨハン・ミヒャエルは、お人よしで自分のことと娘のことしか頭になく、奥さんのエリーザベト(旧姓フォン・ティンマー)は、世にも愚かでばかげたおしゃべり女である。亭主は奥さんの尻に敷かれている。モーツァルトと一緒に辻馬車に乗ったことやビールを飲んだことなどは女房の前で言わないでくれと頼む人だと描かれている。その手紙の中で、「うんざりする」アウエルンハンマー嬢のことが延々述べられている。
もし画家が悪魔をありのまま描こうと思ったら、彼女の顔を頼りにするにちがいありません。――彼女は田舎娘のようにデブで、汗っかきで、吐き気を催すほどです。――肌をまる出しで歩きまわっているので、――「ねえ、こっち見てよ」と、顔にちゃんと書いてあるみたいです。もう、見るのも沢山。盲目になりたいものです。でも――運悪くそっちに目を向いてしまうと、あと一日中、ひどい目に会います。――その時は酒石(注: 吐剤として用いられていた)が入り用です!――それくらい嫌らしく、汚らしく、身の毛のよだつような人です!――ああ、こん畜生め!――
ところで、彼女がどんなにクラヴィーアの演奏をするか――どうしてぼくに手助けしてほしいと頼んだかについては、もう書きましたね。――ぼくは人のためになることなら喜んでしますが、絶えず悩まされるのはごめんです。――彼女はぼくが毎日2時間、一緒に過ごしても満足しません。彼女はぼくに一日中そこに坐っていてほしいと言います。――ぼくは冗談だと思っていましたが、いまでは本気だということが分かります。――たとえば、ぼくが、いつもより少し遅れてきたり、ゆっくりしていられなかったり、そんなようなときに、彼女はやんわりと攻めるなど――なれなれしい態度をとるので、ぼくはそれと気づいたのです。――彼女をもてあそばないためには、丁重に本心を伝えざるをえませんでしたが、――これは何の役にも立たず、彼女のぼくに対する思いはますます深まるばかりです。
結局、ぼくは彼女が変なことを言い出さないかぎり、丁重に接しましたが、彼女の様子がおかしくなり始めると、ぶっきらぼうな態度をとりました。――そうすると、彼女はぼくの手を取って言うのです。「モーツァルトさん、ねえ、そんなに怒らないで。――あなたがなんておっしゃろうと、あたし、本当に好きなんですもの、あなたが。」
街中の人たちが、ぼくらが結婚するのだと言っています。そして、よくまああんな御面相の娘をぼくが選んだものだと呆れています。そんな話がでると、彼女はいつもそれを笑って聞き流していたそうです。でも、ぼくがある人から聞いたことによると、彼女はこの噂を認めた上で、結婚したら一緒に旅行するのだと付け加えていたのです。――これには腹が立ちました。――そこで、こないだとうとうぼくの本心をはっきりと伝え、ぼくの好意に付け込まないでほしいと言い渡しました。――そして、いまはもう毎日ではなく、一日おきに彼女のところへ行っています。こうして徐々に減らすことになるでしょう。――彼女は勝手に惚れ込んだ愚か娘にすぎません。――なにしろ、ぼくと知り合う前、劇場でぼくの演奏(注: 4月3日、ケルントナートーア劇場で催された演奏会)を聞いて、「あした、あの人あたしの家に来るのよ。そうしたらあたし、彼の変奏曲を彼ぴったりの好みで弾いてあげるわ」と言っていたのですからね。――そういうわけで、ぼくは行ってやりませんでした。うぬぼれた言い方だし――彼女は嘘をついていたのですから。翌日ぼくが行くことになっていたなんて、全くぼくの知らなかったことですよ。